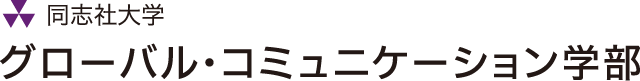近年、「もっと対話が必要だ」「まずは対話の場を設けよう」といった言葉を耳にする機会が増えました。書店には「対話」と名のついた本が所狭しと並び、社会全体で「対話」の重要性が強調されているように感じます。
文部科学省の学習指導要領では、自ら考え、他者と意見を交わしながら理解を深める「対話的な学び」が推奨されています。経済産業省でも、職場のコミュニケーションや企業と投資家の関係構築において、「対話」が重要なキーワードとして位置づけられています。このコラムも、「世界へ通じる対話力。」という言葉がキーワードに掲げられています(最後の句点には、何か意味が込められているのでしょうか。有識者の方、教えてください)。
でも、そもそも「対話」って何でしょう?ただ「話す」ことと、どう違うのでしょうか?私は言語学の中でも「意味論」を専門にしています。意味論では、ある語の意味を明らかにするために、類義語と比較する方法をよく用います。まずは、「対話」と「会話」を比べてみましょう。
日本の劇作家・演出家である平田オリザ氏は、「会話」と「対話」の違いについて次のように述べています。「会話」は、主に人間関係を円滑にするためのものです。例えば、友達との気軽なおしゃべりがそれに該当します。一方、「対話」は、新しい考えや価値観を生み出すことを目的としています。異なる意見や背景を持つ人同士が意見を交わし、すり合わせることで、自分の考えを変えたりする営みです。
この定義を踏まえると、ただ気の合う人と話しているだけでは、「対話」が成立しません。最近では「フィルターバブル」という言葉も広く知られるようになりました。これは、アルゴリズムや自分自身の選択によって、同質的な情報ばかりが集まり、異なる意見や価値観が見えにくくなる現象です。こうした環境では、自分の信念が強化される一方で、新しい視点に触れる機会が失われてしまいます。
では、異なる意見を持つ人と話せばそれでいいのかというと、そう単純でもありません。自分の信念に反する情報を突きつけられたとき、かえってその信念を強めてしまうことがあるのです。これは「バックファイア効果」と呼ばれています。例えば、尊敬している人や「推し」の不祥事が報道されたとき、「これはフェイクニュースだ」と情報を否定することで、かえってその人への信頼を深める。そんな反応を見聞きしたことがあるかもしれません。
こうした現象がどれほど一般的なのかは議論の余地がありますが、少なくとも、自分の考えを変えるというのは、思っている以上に難しいことのようです。人間とは、厄介な生き物ですね。
では、異なる価値観を持つ人と話すだけでは不十分だとしたら、何に気をつければ「対話」が成立するのでしょうか。再び平田オリザ氏の言葉を借りると、「対話」には「相手の価値観を理解しようとすること」と「自分の意見を変えることを厭わないこと」が必要だとされています。これを「対話的な精神」と呼び、自分の意見が変わることに「喜びさえも見いだす態度」(平田 2012)とも述べています。
自分の意見や考えが変わることを、素直に受け入れるのは簡単ではありません。私たちはどうしても、自分の意見を守ろうとしてしまいがちです。というのも、自分の意見や価値観は、これまでの経験や人生の背景と深く結びついているため、それを否定されると、自分自身まで否定されたような気持ちになることがあるからです。実際、私も大学院生の頃、研究発表の場で内容に対する批判を受けた際、それがまるで自分自身への否定のように感じられたことがありました。研究内容と自分自身は別のものだと頭では理解しているつもりでも、それらが一体のものとして捉えられてしまうことがあるのです。
こうした心理的な防衛反応の中で、私たちは自分と異なる意見に出会ったとき、無意識のうちにそれを拒んだり、自分の考えを守ろうとしたりします。実際、「対話の場」と言いながらも、相手の意見に耳を傾けず、互いに自分の主張ばかりを繰り返してしまう場面は少なくありません。あるいは、聞いているように見えても、自分の考えを支持する側面だけを拾い、自分にとって都合の良いように解釈してしまう。そんな「聞いているふり」のような場面もよく見かけます。こうした状況は、「対話」とはほど遠いものです。
自分の考えが変わることに喜びを見いだすという姿勢は、単に相手の理屈を理解しようとするだけでは到達できません。究極的には、自分とは正反対の意見を持つ人の話を聞いた結果、自分の考えが大きく揺らぎ、その意見に共感するようになるかもしれない。それくらいの柔軟さと覚悟が必要なのだと思います。必ずしも自分の立場を根本から覆す必要があるわけではありません。ただ、それくらいの覚悟がなければ、そもそも考えが変わる余地は生まれないと思うのです。
このように、「対話」では、相手の話に耳を傾ける「傾聴」が欠かせません。しかし、それだけでは十分ではありません。その反対側にある「自分の意見の伝え方」も重要です。
このとき大切なのは、相手を説得しようとしたり、自分の考えを押しつけるのではなく、自分自身の立ち位置から意見を述べることだと思います。というのも、意見の主体を曖昧にすることで、自分の発言に対する責任を回避しようとする言い回しが、日常でよく見られるからです。
特に、何かを批判する場面では注意が必要です。例えば、「自分が嫌だからやめるべきだ」という主張を、「良くないことだからやめるべきだ」と言い換えたり、「みんながそう言っている」といった表現で自分の意見を一般化してしまうことがあります。つい、「自分は〜を面白いと思わない」と言う代わりに、「〜は面白くない」と、あたかも客観的な評価であるかのように語ってしまうこと、皆さんにも心当たりがあるのではないでしょうか。
また、手垢のついた話法を無批判に借用することで、自分の言葉としての責任を回避するケースも見受けられます。たとえば、「教員は社会を知らない」という批判があります。確かに、私のように一般企業で働いた経験のない教員は、企業の論理や慣習に通じていません。しかし、そもそも「社会を知らない」とはどういう意味でしょうか?企業で働くことだけが「社会」であり、学校は「社会」ではないのでしょうか?
教員以外にも、一般企業に属さない職業は数多くあります。それにもかかわらず、なぜ教員だけが「社会を知らない」という非難を受けるのでしょうか。おそらく、その言葉を使う人は、教員に対して何らかの不満を抱えており、手近な表現をそのまま借用しているだけなのではないでしょうか。しかし、もし本当に不満があるのなら、自分の頭で考え、自分の紡いだ言葉で、自分の意見として語るべきです。そうでなければ、相手に真意は伝わりません。 「対話」の目的は、相手を言い負かすことでも、勝ち負けを決めることでもありません。むしろ、互いの立場や考えを差し出し合い、理解を深めていく営みです。だからこそ、「自分はこう思う」と自分の立ち位置を明確にしたうえで話すことが重要なのです。それは、自分の発言に責任を持つということでもあります。
理論物理学者 David Bohmは、著書『On Dialogue』で、dialogue と discussion の違いについて次のように述べています(なお、意味論者としては日本語の「対話」と英語の dialogue の意味の違いも気になりますが、ここではその違いには立ち入りません)。
Bohmによれば、discussion はピンポンの試合のようなもので、勝敗を決することが目的です。一方、dialogue は “[N]obody is trying to win. We are not playing a game against each other, but with each other” (Bohm & Weinberg 2004: 7) という姿勢に基づいています。つまり、dialogue あるいは「対話」を「共にプレーする」ものとして成立させるためには、考え方や価値観の不一致を隠すことなく、自分の立場や考えを表明し、それを相手と共有することが必要です。
とはいえ、相手と異なる意見を述べるのは、やはり簡単ではありません。特に日本の文化では、相手に同意することや、同じ考えを共有していることを示すことが好ましいとされる傾向があります(Wierzbicka 1997)。平田オリザ氏も、日本では「対話」が生まれにくいことを指摘しています。
こうした向かい風の中、皆さんはどんな状況であれば、自分の考えを表明してもいいと思えるでしょうか?それが、目の前の相手や世間一般の考えと食い違っていたとしても、安心して話せると感じられるのは、きっと自分の存在が脅かされないという感覚がある場や、そうした安心感を与えてくれる人との関係の中ではないでしょうか。
それでも、どれほど信頼できる相手であっても、いつでも自分の意見を打ち明けられるわけではありません。大きな信頼は「対話」を可能にするための十分条件ではなく、あくまで必要条件にすぎないように思えます。
このように、「対話」には、自分の意見が変わることを潔しとする姿勢に加えて、異なる意見を安心して打ち明けられるような信頼関係も欠かせません。そう考えると、「対話」とは「まずは対話の場を設けよう」といった一言で簡単に始められるようなものではなく、じっくりと時間をかけて築いていく関係性の中で、ようやく可能になる営みなのかもしれません。
さて、話が少し広がってきたところで、今回のテーマに立ち返ってみましょう。キーワードは「世界に通用する対話力。」でした(最後の句点の意味が、まだ気になっています)。私がこのコラムを通して問いたかったのは、「対話」とはそんなに簡単にできるものなのか?ということです。ここまで偉そうに語ってきましたが、自分も「対話」なんてほとんどできていませんし、まだまだ勉強中の身です。
「世界に通用する対話力。」という壮大な目標の前に、考えてみてほしいのは、「世界」の前に「自分の身の回り」で、「会話」ではなく「対話」ができているかどうかです。「グローバル」コミュニケーション学部だからこそ、まずは「ローカル」な関係性の中から、「対話」の力を育んでほしいと思います。つまり、あなたの最も身近で、最も信頼できる、そして最も大切な人の意見に対して、真剣に耳を傾けること。そして、自分の意見が変わることに喜びを見いだしながら、自分の考えを深めたり、柔軟に変化させたりすること。それと同時に、相手との価値観の不一致を恐れず、自分の言葉で、自分自身の立場から、自分の考えを述べること。それが、「対話」への第一歩なのかもしれません。
このメッセージを通じて、皆さんの考えや価値観に少しでも揺らぎや変化が生まれたら、嬉しく思います。そして私自身も、皆さんの考えを聞くことで、自分の思考をさらに磨いていきたいと思っています。 もし何か感じたこと、考えたことがあれば、ぜひお聞かせください。