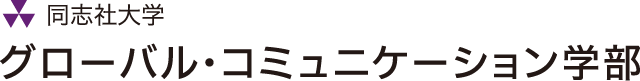広漠としたインターネット空間の片隅にある、こんなコラムに辿り着きながら、「いや私は語学学習にはてんで興味がない」などという人はいないでしょう。そこで今回は、京都の、とある私立大学に勤める「私」さんの語学遍歴を紹介します。
「私」さんの異国語との出会いは、やはり英語でした。今では世界の共通語lingua francaと呼ばれる英語ですが、高校時代の「私」さん、ほとんど勉強をしません。他の楽しい事ばかりが目に付き、テストのための勉強が苦痛でしかない。英語も受験科目以上のものではなかったのです。とはいうものの「私」さんにしても、昼休みに寝転がりながら、英語の小説を読みふける先輩、つまり“語学を楽しめる”人の姿を目の当たりにしていたはずなのですが。
当然ながら希望する大学に入れるような成績は取れません。けれど大学に入らなければ、一生の仕事と思い定めた「ブンガク」の勉強を合法的にやれないので、仕方なしに1年間受験英語に邁進します。「私」さん、努力の甲斐合って運良く志望校のひとつに合格。ところが入学先の大学、最初の1年は週2回の会話が必修、つまり英語を喋らないと卒業できない仕組みになっている。しかも担当になった講師は、「知っている日本語はバカとマージャンだけよ」というアメリカ人女性。ネイティブ教員に習うなど初めての「私」さん、へどもどしながらも「r」の発音の特訓を受けます。何しろそれまでRとLの違いなど意味のない世界(これをRholambdazismusという)に生きてきたわけですから、何度も「No !」、「No !」といわれる。見方によっては一種の公開処刑でしたが、何とかクリア、受講生仲間と課題の英語劇もやりきり、成績も「優」を貰い、立川あたりから電車に乗ってくる米兵の問いかけに怖じ気をふるうこともなくなっていました。しかし、いいことは続かないもので2年次の英語講読は本当に退屈きわまりない。ただ読んで訳すだけ。新しいやり方で言語を習得する“楽しみ”は失せています。元の黙阿弥とはこのことで、すっかり英語や英語で書かれたものにも興味がなくなっていました。
それも当然のことで、「私」さんは週6コマの初級ドイツ語授業という試練を乗り越え、二年生になっています。おぼつかないながらもドイツ語で小説やエッセイを読むようになっています。新しく学んだ言語で何かが出来る、少なくとも「ブンガク」作品に直接、触れている気がしている。「ドイツ語は構文がこんなにゴツゴツしていて、音もなんだか金属的に硬質で」などと生意気なことを感じ始めているのですから、いよいよ深みにはまり込んでいきます。
忘れてならないのは、中学時代の恩師(英語)から大学の入学祝いに、革装の独和辞典(著者の名をとって「キムラ・サガラ」と呼ばれた)と母校の卒業生で「大」のつくドイツ語学者、関口存男の「新ドイツ語大講座」(上巻)を頂いたことです。
その後、「私」さんは、関口「新ドイツ語大講座」の中巻(読解篇)を斜め読みにし、下巻(高級文法篇)は何度も読み返しながら大学院までドイツ語・ドイツ文学とつきあい続けます。しかしそうなると、ドイツ語は楽しみというよりも仕事の道具に近くなってきます。「私」さんが研究対象とした思想家の複雑な考えや、文学作品の構造を読み解くための道具となっていきます。
そうこうしているうちに縁あって、「私」さんはH島大学に職を得、さらに縁あって京都のD大学に勤めることになります。語学教師の生活にやや落ち着きがでてきた頃に、なんだか虫が騒ぎだします。新たな語学がやってみたい。しかも、音声主体でやってみたい、なんと言っても西欧語は音声だからなあ、と考え始めます。そうなるとフランス語しかありません。けれど、どこかの教室に通って習うには時間がありません。毎朝NHKのラジオで「フランス語講座」を聞くことにしました。初級編は対話文で出来ていますので、その対話をすべてノートに書き写し、それに発音を書き込む、語義も書き込んでおく。それから放送を聞いて一緒に発音をしてみる。カード式の単語帳も作る。暇があればそれをひろげて暗唱する。ですが、この時点で「私」さんは二児の父親(つまりいいオッサン)です。夏休みに子連れで帰省しても、単語帳をひろげてモゴモゴ云っています。それが義妹の目にとまり、「お義兄さん、ずいぶん懐かしいことをしてますね」とからかわれる始末。しかしこれを半年間続けると、たいぶ聞きとれるようになり、簡単な映画なら字幕なしで意味が分かるような気がしてきます。ところがやはりいいことは続きません。ドイツ語を使った研究に戻らないといけなくなります。愛しいフランス語は一時保存の運命です。
しばらくして研究に区切りがつくと(むしろ研究が苦しくて逃げ出したくなると)、「私」さん、またしても新しいことがしたいと思い始めます。そのころ語学書にしては法外に売れた本がありました。逸見喜一郎「ラテン語のはなし―通読できるラテン語文法」(大修館)です。この本にたちまち魅了された「私」さん、通読した後になお、もう一度読んで文法解説部分をノートに写します。いよいよ深みにはまり独習書を探します。古典語の教本は、みな大学の教科書用に書かれています。つまり答えが載っていないのです。やっと見つけた独習書は、小林標「独習者のための楽しく学ぶラテン語」(大学書林)でした。「私」さん、ついに先生なしでラテン語修行を始めます。本業そっちのけで熱中し、自分の論文にラテン語の章句を引用し、その意味や構造が説明できる程度まで勉強します。しかし、しかし、またしてもいいことは続きません。ドイツ語を使った別の研究テーマが見つかったのです。愛するラテン語は塩漬けの運命です。
英語、ドイツ語、フランス語、ラテン語と遍歴した後の「私」さんに残されたのは? そうです、「言語の女王」、古典ギリシア語です。なぜ「女王」なのでしょう?ドイツ語の「言語Sprache」は女性名詞なので、「言語の王様(男性名詞)」ではちと具合が悪いのです。では、なぜギリシア語だったのでしょうか?それは「私」さんの読書癖に由来します。「饗宴」とか「ソクラテスの弁明」などで有名な哲学者プラトンには,ひときわ不思議な対話編「パイドン」があります。これは「魂の不死」を論じたものです。父母を相ついで見送った「私」さんは、ワタシはプラトンをギリシア語で読むノダ、と目標を定めます。しかし1年みっちりやったつもりがいっこうに頭に入ってこない。語学は不得手ではないと自信を持っていたはずの「私」さん、大いに困惑します。そのうち「古典ギリシア語なんて原始的だ」、「こんな不規則変化ばかりの言語など、滅びて当然だ」と、ギリシア語そのものに八つ当たりをはじめます。ネイティヴ・スピーカーは絶無なのですから、文句・不平・不満の持って行き先がないのです。ギリシア語の全体像が一向にみえないまま、ギリシア語戦争はいったん休戦。このときすでに「私」さんは「アラカン」の年齢です。ギリシア語は塩漬けどころか、もはや荒地状態で放置されました。
それでも諦めきれず、またしても先生に個人教授を願い出て、さらに2年間励みます。文法の再学習に1年、初級読本に1年を費やし、今は高津春繁「基礎ギリシア語文法・ギリシア語読本」(合本版、北星堂書店)を手にギリシア語との(小規模な)格闘を続けています。プラトンをすらすら読むなど、遠い先の話だとようやく気がつきました。目標を高く設定しすぎて、道のりの遠さにかえって絶望していたのです。
ギリシア語学習の連続的な挫折で、「私」さんが気づいたことがもうひとつあります。語学を何かを達成するための手段と考えてしまうと、学習は苦痛でしかなくなってしまうのです。なかなか目標地点に辿りつけないからです。しかし昔から「語学の天才」とか「多言語通(Polyglott)」と呼ばれる人たちがいます。「天与の語学の才」、「不世出の語学者」などと崇められるわけですが、こういう人たちは、どうやら苦労して語学を身に着けたわけではないようなのです。むしろ他人から見たら途轍もない苦役としか思えない語学学習が、彼らには苦にならなかっただけなのです。膨大な学習時間も無駄とは思っていなかったようなのです。実は彼らは苦痛にならないやり方で、“楽しみ”ながら語学を身に着けたのでした。“語学”が“語楽”に通じていたのです。
こうした“語楽”の秘密を垣間見た「私」さん、今では毎朝NHKの「ラジオ英会話」に邁進しています。流暢に喋りたいとか、海外旅行の役に立つとか、仕事でバリバリ使うとか、そんな高い目標はありません。日常的に英語を話す人々の語感を自然に体感すること、それを積み重ねることが現在の目標です。プラトンだって日常の会話にギリシア語を使っていたのですから、この目標は間違ったものではありません。そんな「私」さんは最近、アメリカの美術家Joseph Cornellの日記やメモを読み始めたのですが、省略だらけの英文がなんだか分かるような気がしてきたのです。