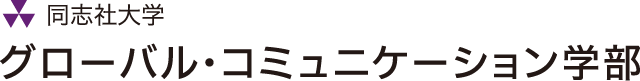この数年間にAIは飛躍的な進化を遂げ、今、この瞬間も進化し続けています。グローバル・コミュニケーション学部が開設されたのは2011年ですが、その時は今のようなAIの進化は考えられませんでした。当時もGoogle翻訳はありましたが、精度は低く、英語から日本語、日本語から英語の翻訳どちらをとっても、どこか不自然で、すんなり理解できるような文章にはなっていませんでした。ところが、今ではかなりの正確さで翻訳や通訳をするアプリを無料で使うことができます。さらには、AIによって自分自身の言葉が瞬時に外国語に変換される技術も開発されています。このような時代に外国語を学ぶ意味があるのかと、疑問に思う人も多いでしょう。でも、こういう時代だからこそ、「ことば」とは何か、「コミュニケーション」とは何かという根本的な問題に立ち戻って、外国語を学ぶ意味について考えてみませんか?
Communicationとは「分かち合う」を意味するラテン語のCommunicareに由来しています。私たちは自分の内にある感情、気持ち、考えなどを他者に伝えたいと思っても、何らかの形で「見える化」しない限り決して伝わりません。私たちは日々のコミュニケーションとは、目に見えない内面を可視化して伝える行為であり、「ことば」とはその手段なのです。「ことば」には、言語以外に、ジェスチャー、アイコンタクト、表情、姿勢など、様々な非言語も含まれます。ファッションや部屋のインテリアでさえも自己を表す「ことば」だと言えます。音楽や芸術もなど、表現のためのすべての媒体は、広い意味での「ことば」なのです。
「大切なものは目に見えない」とは、フランスの作家サン=テグジュペリの『星の王子さま』の一節です。私たちがコミュニケーションを取るとき、本当に表現し、理解したいのは「目に見える」ことばの向こう側にある、「目に見えない」心の内にあって、ことばそのものではありません。ことばがすべてを伝えることができないこともあります。誤解を招くこともあれば、ことばを尽くしても理解し得ないこともあるのです。ただ、それでも他者を理解したい、また、他者に理解してほしいという本源的な欲求を持っているのが人間なのです。
「言語」を学ぶ前の赤ちゃんは、全身を使って自分の気持ちや状態を表現します。空腹、痛み、不快といった感覚を伝えることは、赤ちゃんにとって自らの生存がかかっていると言っても過言ではないくらい大切なことです。それゆえに赤ちゃんは「泣く」、「笑う」ということばを駆使して、自らの欲求や、その欲求が満たされたときの喜びを伝えるのです。けれども、赤ちゃんは成長するにつれて、「泣く」、「笑う」以上に便利な手段があることに気付きます。それが言語です。「お腹がすいたの?」「眠たいの?」と周囲の人々が話しかけてくれる言語を聞きながら、赤ちゃんは欲求を言語で表現していくことを学んでいきます。また、欲求だけではなく、幸せ、喜び、怒り、悲しみといったより複雑な感情や、自らの経験や考えなどを伝える言語を学んで成長していきます。
母語を学んだあと、外国語という別の言語を学ぶとき、私たちはもう一度、言語を知らない赤ちゃんの状態に戻ります。初級者の段階では、身振り手振りといった非言語も総動員して相手に言いたいことを伝えようとするでしょうし、上達するにつれて、より複雑な事柄や気持ちを言語で表現できるようになるでしょう。ことばは文化によって異なります。たとえば「愛情」という感情自体は人類共通の普遍的なものであっても、その感情を表すことばは文化によって様々です。外国語を学ぶとは、単に単語や文法を学ぶのではなく、新しい考え方や価値観、さらには新しい自己表現の方法を学ぶことでもあるのです。
外国語の学習には長い時間と忍耐が必要です。発音を学び、単語を覚え、文字や表記を学び、文法規則を覚える、また、それを使いこなせるように練習を重ねるのは面倒なことです。自動翻訳や通訳などの便利なアプリがある時代に、時間とお金をかけて外国語を学ぶ学部に入るなんて、「コスパ」から考えても「タイパ」から考えても意味がない――そう思う人がいるのも仕方がないのかもしれません。けれども、外国語を学ぶことによって得られるものは計り知れません。ある国・地域の社会や文化を真に理解するためには、その土地で話されている言語の学習が不可欠です。そして、何よりも外国語学習は楽しい経験であり、未知の世界へのわくわくするような冒険でもあるのです。
同志社大学グローバル・コミュニケーション学部で、そんな冒険への一歩を踏み出してみませんか?