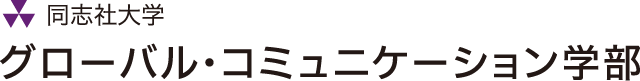留学生レポート
海外各国からGCへ留学中の学生が、日本での学びをレポート。
日本で出合った新鮮な体験を生き生きと伝えます。
柊家の見学レポート/
2025.02.03
- オフキャンパス
- 日本語
- 한국
「社会実習B」の授業の一環で京都を代表する旅館「柊家」を訪れた。幕末文政元年(西暦1818年)に運送、海産物の店を開いたことから商人たち度々、店に泊まったことが柊家のはじまりと言われている。その後「来者如帰」(らいしゃにょき)の理想に、本格的な旅館業を開始し、明治時代から様々な皇族や文人をはじめ、現代では様々な人たちが利用する場所となっている。
사회실습B수업에서 교토를 대표하는 여관 히이라기야를 방문했다.막부말기 1818년에
운송,해산물가게을 열어 가게에서 상인들이 묵었던 것이 지금의 여관으로 발전되었다.
그 후, ‘래자여귀’의 정신으로 메이지시대부터 여러 왕족,문인들을 시작으로 많은 사람들이 이용하는 장소가 되었다.

柊家の玄関から見える「来者如帰」の額
「来者如帰」とは、我が家に帰ってきたように、おくつろぎ頂けますようにという意味で、この旅館に泊まっている間は、他所の部屋ではなく、家のように泊まっていてくださいという京都のおもてなし精神がこの言葉には溶け込んでいると思う。
래자여귀란, 마치 자기 집에 돌아온 것같이 편하게 지내라는 뜻으로 이 여관에 묵는 동안에는 집처럼 편하게 지내라는 교토의 접객정신이 녹아 있다.

ホテルでいうレセプションにあたる空間。柊家を表現している家具が置いてあり、グッズが並んでいた。

旧館から新館に繋がる通路。旧・新の違和感がない。
また、柊家には江戸時代からの旧館と平成に新しくたてられた新館が存在している。旧館のほとんどは江戸時代からのものをそのまま残しており、まるで当時にタイムスリップしたような感覚を与えてくれた。もちろん、200年を超える建築物であるため、最新の施設のように冷・暖房がよく効いたり、便利なAI技術が使われたりしている わけではない。むしろ、現代人にとっては多少不便なところがあるかもしれない。しかし、ただ便利さや効率を追求する最新の建物には存在しない、 昔のものを昔のままに体験できるという、唯一無二の価値がある建物だと思った 。
또한, 히이라기야는 에도시대부터 만들어진 구관과 2000년대에 만들어진 신관이 함께 존재한다.구관은 에도시대의 건물을 그대로 남겨놓고 있어 마치 그 시대로 시간여행을 한 것만 같은 느낌을 받을 수 있다.물론, 200년 넘게 유지되어온 시설이기 때문에 냉난방이 잘되고 편리한 시설이 구비되어 있는 것은 아니다.오히려 천장은 낮고 조명은 어둡고 욕조는 너무나도 좁은 현대인에게는 불편한 점이 많을 지도 모른다. 하지만 옛 것을 불편하다고 유행만을 쫓아서 새로운 것에만 의지하는 것이 아닌, 옛 것을 그대로 지켜 나가고 있다는 것을 보여주고 있었다.

こちらは『雪国』で有名な川端康成 がしばしば宿泊した 部屋。
天井や照明、お風呂はほとんど江戸時代からそのままの状態で守られている 。
部屋から見える庭は、私たちが今まで見たことのある 庭とはまた別の何か感じられた 。「庭」というのは、人がわざと綺麗に飾ったり、直したりして作るのが一般的だと考えている人が多いのではないだろうか。この柊家の庭ももちろん、手入れをしないわけではないが、綺麗で華麗に整えられてはおらず、 「自然」のそのままを見せようとしていた。例えば、石にわざと苔をつけることによって、「人工的」な美よりもまるで美しい山を見たような「自然的」な美を感じることができる。このような日本の「美」の考え方が柊家のあらゆる場所から感じられた。
특히 방에서 보이는 정원은 우리가 지금까지 생각해온 정원과는 또 다른 느낌을 받을 수 가 있었다.정원이라는 것은 보통 사람들이 화려하게 꾸미거나 이쁘게 고쳐서 만드는 것을 상상하고는 한다. 히리라기야 정원도 물론 완전이 사람의 손을 타지 않은 것은 아니지만, 화려하게 꾸미는 정원보다는 자연 그 자체를 보여주고 있었다.예를 들어 돌에 일부러 이끼를 놓아 인공적인 미보다는 아름다운 산을 보는 것처럼 자연미를 느끼게 해준다.
이러한 일본은 미를 히이라기야 에서 보여주고 있다.
それぞれの部屋にある床の間。こちらからも素朴な「美」 が感じられる。

新館の部屋の休憩空間。障子の模様を外の屋根の模様に合わせている。

廊下に飾られた生花。季節によって変わるらしい。
新館の 図書室から見える中庭(写真左)と 図書室に置いているソファー(写真右)。図書室もゆったりできる空間で、ソファーは 、図書室の雰囲気に合わせて制作された カスタムソファーだという 。
柊家では「どうすれば心地よい空間になるだろうか 」考え抜かれており、家具や装飾の配置など 細かい工夫が見られていた。豪華なバラや百合を派手に 廊下に飾るの ではなく、その季節を味わえる野の花がさりげなく生けてあった。 図書室のソファーの配置一つをとっても、どのように置いたらお客様がゆったりできるのかが考え抜かれていた。
또한, 히이라기야에서는 가구나 장식의 배치에서 “어떻게 하면 편안한 공간이 될까”같은 섬세한 노력이 보여진다. 그저 예쁜 꽃을 복도에 꾸며놓는것보단 방문한 시기의 계절을 느낄 수 있는 꽃을 사용하거나, 여관 신관에 위치하고 있는 도서실의 소파 조차도 편안한 공간에 맞춰 그 공간을 표현하고 있었다.

大正時代に活動した小川三知(おがわ・さんち)作。廊下で見ることができるステインドグラス。旧館の雰囲気と合わさって不思議な感覚を与えてくれる 。

家族風呂。私たちが見学した日は冬という季節に合わせて柚子風呂になっていた。
今回の見学は 、高級旅館の内部をじっくりと見るという、それだけでも 素晴らしい経験ではあったが、それよりも日本の寺や神社に共通する 日本の「美」や「おもてなし」を、深く理解できる 貴重な経験であったと思う。よく世間からは、 日本は建前と本音があって、特に京都の人たちはその本音を話さないという噂を聞く。それで、京都で素晴らしいサービスを受けたにも関わらず「何か裏があるのでは… 」と考えてしまう人もいるかもしれない 。しかし、私たちが柊家で経験した「おもてなし」は、 世間から言われているものとは違っていた。最初の玄関から見える 「来者如帰」の額 からわかるように、純粋にお客様自身の家 のようにゆっくりしてほしいという気持ちだった。この無償の心が日本の「おもてなし」であり、私たち現代人が相手を接するときに思い出すべき ことではないだろうか。
이번 견학을 통해 고급여관을 다녀온 것만으로 충분히 멋진 경험이 되었지만, 일본의 절이나 신사에 가는 것만으로 느낄 수 없는 일본의 문화를 느낄 수 가 있었다. 세간에서는 일본은 상대방에 들어내는 겉마음과 속마음이 분명하게 존재하고, 특히나 교토사람들은 그 정도가 세다 라고들 한다.그래서 교토에서 어떤 서비스를 받아도 “뭐 다른 속마음이 있는게 아니야?”라고 말하는 사람들도 있을 것이다. 하지만 이번 견학에서 느낀 경험은 무언가 달랐다. 히이라기야 현관에서 본 래자여귀의 글귀처럼 어떤 대가를 목적으로 좋은 물건을 놓고, 꾸미는 것이 아닌 그저 상대방이 편하게 지내고 가라는 마음이었다.이 대가 없는 마음이 일본은 접객 ‘오모테나시’를 나타내고 현대인들이 상대방을 대할 때 가져야 할 마음이지 않을까. 이
日本語コース3年 シムヒョンスさん