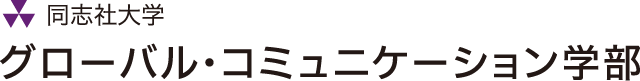留学生レポート
海外各国からGCへ留学中の学生が、日本での学びをレポート。
日本で出合った新鮮な体験を生き生きと伝えます。
多文化共生プロジェクトから学んだコミュニケーション術/
2025.09.04
- မြန်မာဘာသာ
- オフキャンパス
- 日本語
- 简体中文
- 香港粤語
- 한국
この度、私たちは同志社大学、同志社女子大学、京田辺市とともに、多文化共生イベント「YesかNoで深める多文化トーク」を成功裏に開催することができました。
ここは、主に企画から実施に至るまでの「プロセス」で私たちが何を学び、何に苦労したのかを振り返ってみたいと思います。特に、将来日本で働くことを目指す留学生の皆さんにとって、教科書では学べない「現場のリアル」を共有できればと思います。
从多元文化共生项目中学会的沟通技巧
2025年7月,我们与同志社大学、同志社女子大学以及京田边市共同成功举办了“Yes or No——深化多元文化交流”这一多元文化共生主题活动。
在这里,我们想重点回顾一下从策划到实施的整个过程中,我们有哪些收获,又遇到了哪些困难。特别是我们希望能与未来有志在日本工作的各位留学生朋友们,分享一些在教科书上学不到的“第一线的真实情况”。
다문화 공생 프로젝트에서 배운 소통 방법
이번에 저희는 도시샤대학교, 도시샤여자대학교, 교타나베시와 함께 다문화 공생 이벤트 「Yes or No로 깊어지는 다문화 토크」를 성공적으로 개최할 수 있었습니다.
여기에서는 주로 기획에서 실행까지의 ‘과정’ 속에서 저희가 무엇을 배우고, 어떤 점에서 어려움을 겪었는지를 되돌아보고자 합니다. 특히 앞으로 일본에서 일하기를 목표로 하는 유학생들에게, 교과서에서는 배울 수 없는 ‘현장의 현실’을 공유될 수 있기를 바랍니다.
從多元文化共融活動中學到嘅溝通技巧
我地同志社大學、同志社女子大學以及京田邊市合作,成功舉辦咗今次多元文化共融活動。
喺以下嘅段落,主要想回顧一下由企劃到實施嘅過程裏面,我地有邊啲收獲,又遇到點樣嘅困難。特別係希望為將來打算喺日本做嘢嘅留學生,傳遞教科書入面學唔到嘅「真實情況」。
မျိုးစုံယဥ်ကျေးမှုပူးပေါင်းနေထိုင်မှုစီမံကိန်းမှလေ့လာရရှိသောလူမှုဆက်ဆံရေးနည်းပညာများ
ကျွန်ုပ်တို့သည် Doshishaတက္ကသိုလ်၊ Doshishaအမျိုးသမီးတက္ကသိုလ်နှင့် ကျိုတနာဘေမြို့အစိုးရတို့နှင့်ပူးပေါင်းကာ “Yes သို့မဟုတ် No ဖြင့်နက်နဲစွာစဥ်းစားသည့် ယဥ်ကျေးမှုဆွေးနွေးပွဲ”အခမ်းအနားကိုအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့သည်။ဤအစီရင်ခံစာတွင်အဓိကအားဖြင့်အစီအစဥ်စတင်စီမံခန့်ခွဲရာမှလက်တွေ့ကျင်းပသည်အထိပြုလုပ်ခဲ့သောလုပ်ငန်းစဥ်မှ မည်သို့လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်၊ မည်သည့် အခက်အခဲများကိုကြုံတွေ့ခဲ့သည်တို့ကို ပြန်လည်သုံးသပ်မည်ဖြစ်သည်။အထူးသဖြင့်အနာဂတ်တွင်ဂျပန်နိုင်ငံတွင်အလုပ်လုပ်ရန်ရည်မှန်းထားသည့်နိုင်ငံခြားသားကျောင်းသား/သူများအတွက် ဖတ်စာအုပ်များတွင်မတွေ့နိုင်သော”အမှန်တကယ်”
အတွေ့အကြုံ”ကို မျှဝေလိုပါသည်။
「そこまで考えるのか!」― 日本の“入念な準備”という壁と武器
このプロジェクトを通して最初に痛感したのは、日本の仕事における準備の緻密さです。
授業で企画が選ばれた当初、私たちはイベントの大枠を決め、満足していました。しかし、大学の先生方や京田辺市の担当者の方との打ち合わせが始まると、私たちの「考え」がいかに浅かったかを思い知らされました。例えば、「参加者へどうやってわかりやすく伝えるのか?」、「チラシのこの表現は、外国人でもうまく理解できるのか?」、「当日の役割分担、5分単位でタイムテーブルを作ってください」など。自分では「ここまで考えた」と思っていても、その一歩、二歩先のリスクや可能性を常に指摘されました。正直、何度も「面倒くさいなぁ」と感じました。しかし、プロジェクトが進むにつれ、この緻密さが、関係者全員の安心感と当日のスムーズな運営に繋がるのだと理解しました。
さらに、このことから、「一人で完璧な計画を立てようとしないこと」が気付かせました。自分の視点だけでは、必ず漏れが出ます。だからこそ、とにかくチームのメンバーと頻繁に、そして率直に話し合うことが不可欠でした。「これは考えすぎかな?」と思うような小さな懸念でも口に出すことで、他の誰かが拾ってくれ、より強固な計画へと繋がっていったのです。
多くの方のご意見をもとに検討をした制作途中のチラシ
協働の生命線:「確認」と「報連相」の本当の意味
複数の組織が関わるプロジェクトでは、コミュニケーションの難しさが常に付きまといます。特に「言ったはず」「分かっているだろう」という思い込みは、後で大きなトラブルの原因になります。私たちはこのプロジェクトを通して、「確認」と「報連相(報告・連絡・相談)」の重要性も身をもって学びました。
「確認」は、相手への配慮である
打ち合わせで何かを決めた後、私たちは必ず議事録を作成し、「本日の打ち合わせでは、〇〇が△△と決まりました。この認識で合っていますでしょうか?」と、メールで関係者全員に「確認」するプロセスを徹底しました。
最初は手間だと感じましたが、この一手間が「認識のズレ」を防ぎ、全員が同じ方向を向いて進むための羅針盤の役割を果たしました。社会人として働く上で「確認する」という行為は、自分のためだけでなく、「あなたの意図を正確に理解したい」という相手への敬意と配慮の表明なのだと感じます。
「報連相」は、信頼関係の土台である
小さな進捗や少しの変更点でも、こまめにチーム内で共有する「報告・連絡」。そして、一人で判断に迷った時に「どう思いますか?」と助けを求める「相談」。この「報連相」が、チーム内の信頼関係を築きました。
特に「相談」は勇気がいることですが、「相談してくれてありがとう。一緒に考えよう」と言ってもらえた時、一人で抱え込まずにチームで仕事をする心強さを感じました。これは、将来会社で働く上でも、自分を守り、チームのパフォーマンスを最大化するために不可欠なスキルだと確信しています。
達成感と、これからの自分への期待
イベント当日、参加者の皆さんが笑顔で交流している姿を見た時の達成感は、言葉にできないものでした。しかし、それ以上に大きな収穫だったのは、この困難なプロセスを、国籍も立場も違う人々と協力して乗り越えられたという事実そのものです。
総じて、この経験から得られたのは、単なるイベント運営のノウハウではありません。相手の意図を深く読み解こうとする姿勢、誤解を恐れずに確認する勇気、そしてチームを信頼して頼る力。これらはすべて、日本という異文化の環境でプロフェッショナルとして働くための、実践的な武器になると信じています。
今後の抱負として、この経験を糧に、日本での就職活動、そしてその先のキャリアに活かしていきたいです。異なる文化背景を持つ人々の間に立ち、このプロジェクトで学んだ緻密な準備と丁寧なコミュニケーションを実践することで、円滑な協働を生み出す「架け橋」のような存在になることが私の目標です。
日本語コース 3年 コ バイコウさん、イ ヘリさん、ン ホイチンさん、ティリ アウン ナインさん