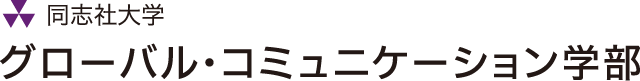留学生レポート
海外各国からGCへ留学中の学生が、日本での学びをレポート。
日本で出合った新鮮な体験を生き生きと伝えます。
多文化共生の「現場」づくりレポート:『YesかNoで深める多文化トーク』の挑戦と学び/
2025.09.04
- မြန်မာဘာသာ
- オフキャンパス
- 日本語
- 简体中文
- 香港粤語
- 한국
2025年7月29日、私たちは同志社大学、同志社女子大学、そして京田辺市の三者で、多文化共生イベント「YesかNoで深める多文化トーク」を開催しました。この企画は、大学の授業での小さな気づきから始まり、地域を巻き込んだ実践へと発展したものです。ここでは、企画の立ち上げから実施後の振り返りまでを共有し、多文化共生に関心を持つ方々にとって、次の一歩を踏み出すためのヒントとなれば幸いです!
打造多元文化共生的“第一线”报告:『“Yes or No”——深化多元文化交流』活动的挑战与收获
2025年7月29日,我们与同志社大学、同志社女子大学以及京田边市三方,共同举办了名为“Yes or No——深化多元文化交流”的多元文化共生主题活动。这个企划源于大学课堂上的一个小小发现,并最终发展成为一场联动整个地区的实践活动。在此,我想分享一下从计划开始到实际落地的过程,以及一些反思,希望对与多文化交流有兴趣的读者们迈出下一步有所启发。
다문화 공생의 ‘현장’ 만들기 레포트: 『Yes or No로 깊어지는 다문화 토크』의 도전과 배움
2025년 7월 29일, 저희는 도시샤대학교, 도시샤여자대학교, 그리고 교타나베시가 함께 다문화 공생 이벤트 「Yes or No로 깊어지는 다문화 토크」를 개최했습니다.
이 기획은 대학 수업 속 작은 깨달음에서 출발해, 지역을 아우르는 실천으로 발전 했습니다. 기획의 시작부터 실행 후 되돌아본 것들을 공유하여, 다문화 공생에 관심 있는 분들에게 다음 한 걸음을 내딛는 힌트가 되기를 바랍니다!
打造多元文化共融嘅現場報告︰『Yes or No? 深化多元文化文流』活動中嘅挑戰同體會
2025年7月29,我地同志社大學﹑同志社女子大學同京田邊市三方,合作舉辦咗一個多元文化共融活動—— 「Yes or No? 深化多元文化文流」。呢個計劃,係由大學堂上一個小小嘅發現開始,擴展變成一場牽涉社區活化嘅活動。喺呢到,我地會分享今次企劃嘅起步到結束之後反思嘅過程,希望可以為關注多元文化共融嘅大家,喺踏出一步作出行動嘅時候成為參考,得到啟發。
မျိုးစုံယဥ်ကျေးမှုပူးပေါင်းနေထိုင်သော”နေရာ”တည်ဆောက်ခြင်းအစီရင်ခံစာ “Yes သို့မဟုတ် No ဖြင့် နက်နဲစွာစဉ်းစားသည့် ယဉ်ကျေးမှု မျှဝေဆွေးနွေးပွဲ”မှ အတွေ့အကြုံနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ
၂၀၂၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက်နေ့တွင် Doshisha တက္ကသိုလ် ၊Doshisha အမျိုးသမီးတက္ကသိုလ် နှင့် ကျိုတနာဘေမြို့အစိုးရတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်၍ “Yes သို့မဟုတ် No ဖြင့် နက်နဲစွာစဉ်းစားသည့် ယဉ်ကျေးမှုမျှဝေဆွေးနွေးပွဲ”ဟုခေါ်ဆိုသောမျိုးစုံယဥ်ကျေးမှုဆွေးနွေးပွဲအခမ်းအနားကိုကျင်းပခဲ့သည်။ ဤအစီအစဥ်သည်တက္ကသိုလ်၏အတန်းသင်ခန်းစာမှပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည့် သေးငယ်သည့် သတိပေးအမြင်တစ်ခုမှစတင်ပြီးနေရာခံအသိုင်းအဝိုင်းများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သည့်အထိအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့သောစီမံကိန်းတစ်ခုအဖြစ်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ဤအစီရင်ခံစာတွင်စီမံကိန်းစတင်ချိန်မှပြီးမြောက်ချိန်အထိလုပ်ဆောင်မှုများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ကာမျှဝေခြင်းဖြင့်မျိုးစုံယဥ်ကျေးမှုများပူးပေါင်းနေထိုင်ခြင်းနှင့်ပတ်သတ်ပြီးစိတ်ဝင်စားသူများအတွက်ခြေတစ်လှမ်းအဆက်ဖြတ်နိုင်ရန်အထောက်အကူဖြစ်စေမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
企画の原点:日本語教室で発見した「見えない壁」
この企画の出発点は、2024年12月の「ワークショップ現代日本社会2」という授業でした。当初、私たちは「地域と外国人留学生を結ぶ活動」という大きなテーマを前に、具体的なアイデアを見つけられずにいました。そんな中、メンバーの一人が「まずは現場に行ってみよう」と提案し、私たちは京田辺市の日本語教室を訪問しました。
そこで担当者の方にお話を伺う中で、一つの課題が見えてきました。それは「言語の壁による、参加者同士の相互理解の不足」です。日本語レベルに差があるため、どうしても会話が一方的になったり、深い意見交換が難しかったりするとのことでした。
この課題を解決するため、私たちは「誰もが参加しやすいトーク形式のイベント」を提案しました。複雑な日本語能力を必要とせず、身振り手振りも交えながら直感的に意思表示ができる「Yes/No」形式を採用し、互いの文化背景や価値観の違いを楽しみながら知ることを目標としました。この企画が授業内で評価され、実施の機会を得ることができました。
イベントの成果:参加者の声が示す「相互理解」の芽生え
イベント実施に向けて、京田辺市役所や同志社女子大学の方々と何度も協議を重ね、準備を進めました。そして迎えた当日、イベントは大きなトラブルもなく進めることができました。
終了後に実施したアンケートからは、私たちが目標としていた成果が明確に表れていました。例えば、「自分と異なる国の人にとっては、当たり前のことが真っ逆で驚いた」「初めて聞く話ばかりで、とても面白かった」など。これらの声から、参加者が互いの文化の違いを「壁」としてではなく「発見」としてポジティブに捉え、楽しみながら相互理解を深めるという当初の目的が達成できたと確信しています。さらに、私たちが最も嬉しく感じたのは、今回のイベントで初めて日本語教室に来られた地域の方が、日本語教室の温かい雰囲気に感銘を受け、「今後、この教室の活動に参加してみたい」と話してくださいました。イベントが一回のみで終わらず、地域コミュニティと人々を繋ぐ新たなきっかけを生み出せたことは、大きな成功点ではないかと思います。
同志社女子大学のゼミ学生との打ち合わせの様子
浮き彫りになった課題:「話せない」人の声をどう拾うか
一方で、明確な反省点も見つかりました。それは、日本語での会話がまだ難しい参加者へのフォローが不十分だった点です。
私たちはこの問題を事前に想定し、翻訳ツールを用意したり、参加者同士でサポートし合うよう促したりといった対策を講じていました。実際に学習者がスマートフォンの翻訳機能を使って、自分で発言したり、他の参加者の発言を理解しようとしたりしている様子も見られました。しかし、日本語能力の高い参加者に発言が集中してしまい、そうでない参加者が意見を言いにくい状況も生まれてしまいました。
この経験を通じて、「誰もが気兼ねなく参加できる環境」を作ることの難しさを痛感しました。単にツールを用意するだけでなく、例えば、「少人数のグループに分かれて、話しやすい雰囲気を作る」、「母語で話してもらい、他のメンバーがその意図を汲み取る努力をする」など、より踏み込んだ工夫が必要だったかもしれません。
今後の抱負:一過性のイベントから、持続的な拠点へ
今回の活動を通して、地域の日本語教室が持つ大きな可能性を再認識しました。日本語を学ぶだけの場所ではなく、多様な背景を持つ人々が出会い、理解し合う「多文化共生の拠点」となり得る場所です。
今後は、この日本語教室が地域の方々にもっと広く知られ、その影響力をさらに広げていくための一助となりたいと考えています。私自身も、学業に余裕があれば支援者として継続的に関わり、今回の反省点を活かして、より良い教室づくりに貢献していきたいです。
今回このような機会を与えてくださった、京田辺市役所、京都府国際センターのみなさま、そして、「京田辺国際ふれあいネット」のみなさま、本当にどうもありがとうございます。それから、私たちの企画を一緒に検討してくださった、同志社女子大学の岩坂ゼミのみなさまにもお礼を申し上げます。
ここまでご覧いただきありがとうございました。このレポートが、多文化共生に関心を持つ皆さんの活動のヒントになれば幸いです。
日本語コース 3年 コ バイコウさん、イ ヘリさん、ン ホイチンさん、ティリ アウン ナインさん